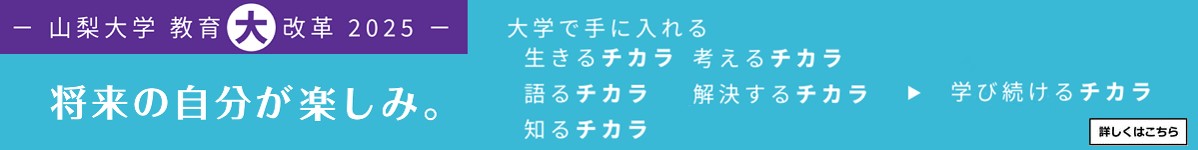
令和6年度第1回教養教育講座
「どのようにして恐竜を科学するのか〜最新の恐竜研究の現場から〜」を開催
2024年6月12日(水)、岡山理科大学生物地球学部地球学科所属の林昭次准教授をお迎えし、令和6年度第1回教養教育講座「どのようにして恐竜を科学するのか〜最新の恐竜研究の現場から〜」を開催しました。
ご講演は恐竜研究の歴史についてのお話から始まりました。恐竜研究は1824年にイギリスで始まりましたが(今年でちょうど200年!)、日本では1936年にようやく最初の科学論文が発表されたばかりで、研究の歴史はまだ浅いといえます。一方で、林先生が留学されていたドイツでは研究が非常に進んでいて、有名なプラテオサウルスや始祖鳥は、19世紀にはすでに発見されていたそうです。
続いて、林先生が参加されているモンゴルでの恐竜発掘プロジェクトが紹介されました。ウランバートルから発掘現場のゴビ砂漠までは、なんと車で20時間もかかる過酷な道のりですが、現地では「たけのこ掘り」をするように、面白いほど多くの化石が見つかるそうです。発掘の方法は、ひたすら現場を歩いて探すプロスペクティングと、千枚通しで丁寧に化石を掘り起こす作業に分かれます。発掘といえばツルハシを力一杯振り下ろすイメージがありましたが、そんな乱暴な方法では化石が破損してしまうとのことでした。
恐竜を科学する方法についても興味深いお話が聞けました。絶滅した動物の生態はもう観察することができませんが、現在生きている人間や動物の骨の形や構造と生態との関連性をもとに、恐竜の生態を推測することはできます。また、恐竜学は実に様々な分野からアプローチのできる研究です。工学分野からのアプローチでは、恐竜の足跡の歩幅から恐竜の歩行をシミュレーションすることができ、生物分野からのアプローチでは、恐竜が鳥類と同様に気のうを有していたことが解明されました。
恐竜の骨内部の組織を観察することで骨の機能や成長について研究する、林先生のご専門であるボーンヒストロジー(骨組織学)についてもご説明いただきました。骨の組織にも木のような年輪状の構造が見られ、そこから恐竜の年齢や成長速度が推定できるそうです。例えば、7メートル成長するのにワニが50年かかるのに対して、恐竜の中にはわずか10年しか要しないものがいたことから、恐竜は骨代謝の高い動物であったことがわかります。
最後に、恐竜研究の意義についても興味深い言及がなされました。近年非常に人気のある福井県立恐竜博物館の年間入場者数は90万人に及ぶとのこと。まさに福井県の一大観光事業となっており、恐竜がもたらす経済効果の大きさには驚くべきものがあります。また、恐竜の研究には化学・地学・物理学・生物学など様々な分野からのアプローチができるため、子どもたちの理科離れを食い止める力があるのではないかとのお話でした。そのうえ、恐竜は地球上でもっとも長きにわたって活動した大型脊椎動物であり、大陸の配置や気候の変化に対して恐竜がどのように適応したのかがわかれば、地球温暖化の影響や生物多様性の保全に向けて、人類が取り組むべき課題も見えてきます。恐竜の研究は単に過去のロマンを追い求めるものではなく、間違いなく現在の私たちの社会に役立つものです、との一言でご講演が締め括られました。
「恐竜」という、学生にとっても教職員にとっても関心の高い講演テーマだったこともあり、ご講演後には非常に多くのご質問が寄せられました。林先生はご自身の体験をもとに、研究を進めるためだけでなく文化交流の観点からも、ドイツなど海外への留学を学生に強く勧めていたことが印象的でした。